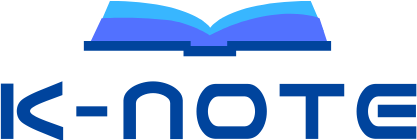プロのライターには簡潔で明瞭な文書が求められますが、気を抜くとやってしまいがちな冗長表現があります。そのうちの一つが、この「〜することができる」。
文法的に間違ってはいないものの、多くのケースで可能の「れる・られる」に置き換えることができます(←と、早速やらかしてみました)。
Webライティングで「〜することができる」が冗長とされる要因
Web ライティングの現場では「〜することができる」が冗長表現とみなされやすいです。だって、「英語を話すことができます」は、「英語を話せます」で通じますし、「高速でタイピングすることができます」は、「高速でタイピングできます」でいいですよね。
こういう表現が鬼の首を取ったかのように指摘されるようになった背景には、4つの要因があると考えられます。
- スマートフォン閲覧が主流となり、冗長な語がスクロール回数を増やして離脱率を押し上げやすい
- 文字数指定案件で水増しを疑われるとクライアントの信頼を損なう
- 英語直訳調の硬さが読者との心理的距離を広げる
- 「〜こと」で名詞化すると行為の躍動感が弱まり、説得力が薄れる
以上から簡潔表現が奨励されますが、過剰な削減は文脈を削り、文章の呼吸を損ねる副作用も見逃せません。SEO は文章構造や読了率も評価指標に含めるため、均衡の取れた視点が欠かせません。特に専門性の高い記事では、情報の精度と簡潔さが綱引きになる局面で顕在化します。
「できる」では代替し切れないニュアンスも
「〜することができる」と「できる」は、同じ可能を示しつつ焦点の置き方が異なります。
「〜することができる」は動作そのものを主語化して強調し、達成すべき行為へ視線を集めます。
一方「できる」は主体に光を当て、実行者の能力や状態を前面に押し出します。語感として前者は書き言葉寄りで慎重な響きを帯び、後者は日常的で軽快な印象を伴います。
また可能動詞「〜られる」は尊敬や受動の用法と重なりやすいため、誤読を避けたい場合には「〜することができる」を残す判断が効果的です。たとえば「魚が食べられる」を「魚を食べることができる」と書き換えると主体の混乱を避けられます。
表現が担う役割を丁寧に見極めれば、冗長削減は文章の芯を強める作業へと変わります。書き手は意図を手放さずに表現を選ぶ姿勢が重要です。
活用──あえて「〜することができる」を残す四つの場面
表現を削るだけが正解ではありません。「〜することができる」をあえて残すことで文意が濃くなる局面も存在します。代表的なパターンは次の四つです。
- 行為そのものを強調したいとき
- 尊敬と受動の混同を防ぎたいとき(前述)
- 漢字比率を下げ文章にリズムを与えたいとき
- 読者に選択の自由を示しサービスの柔軟性を訴求したいとき
たとえば「動画を視聴することでスキルを伸ばすことができます」という一文は、努力と結果の因果を強調し、読者の期待値を高めます。
契約書で「解約することができます」と書けば、「選択権を保有できる安心感」を与えるといえます。読者が抱く疑問や不安を先回りで解消する意図が明確であれば、冗長性は説得力へ転化し、ブランドへの信頼を底上げする効果も期待できます。
さいごに:レギュレーションには従うこと!
「〜することができる」は冗長表現として扱われることが多いですが、表現の引き算は目的ではなく手段です。重要なのは読者が情報を誤りなく受け取り、行動を起こしやすいかどうかです。
短縮が適切な場面では潔く削り、動作を強調したい場面では残します。判断基準は文脈、ターゲット、伝えたいニュアンスという三要素の交点に置きます。
もちろん、レギュレーションで「することができる絶対禁止!」であれば、使わないでくださいね。ライター個人のこだわりなどメディアのルールの中では論外ですので。